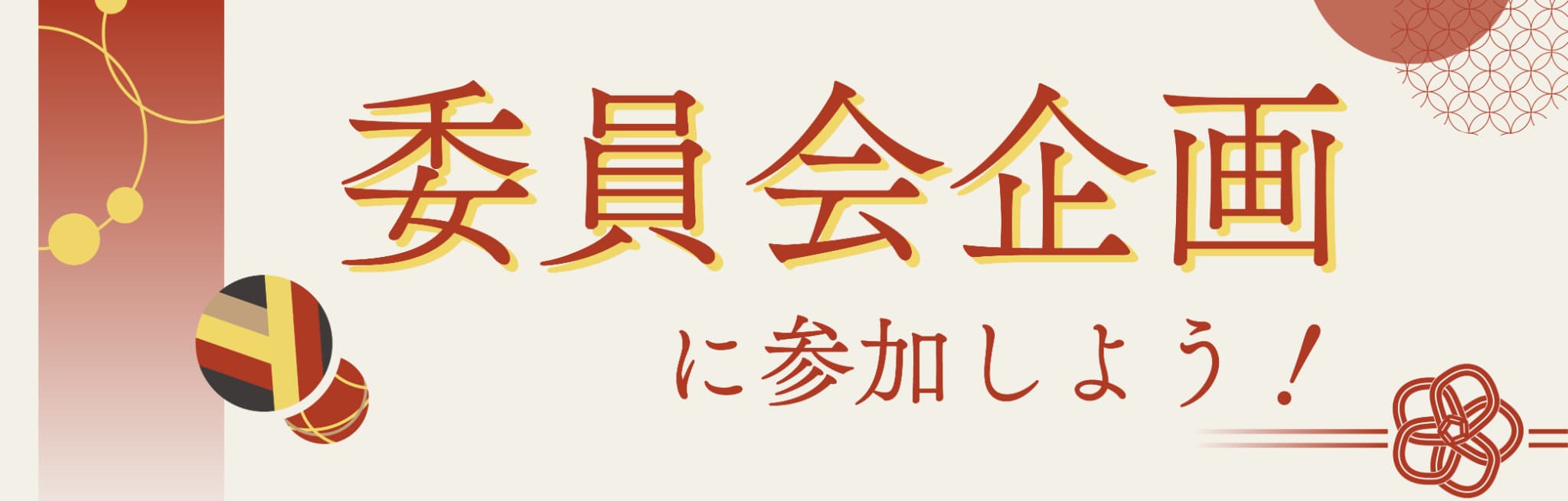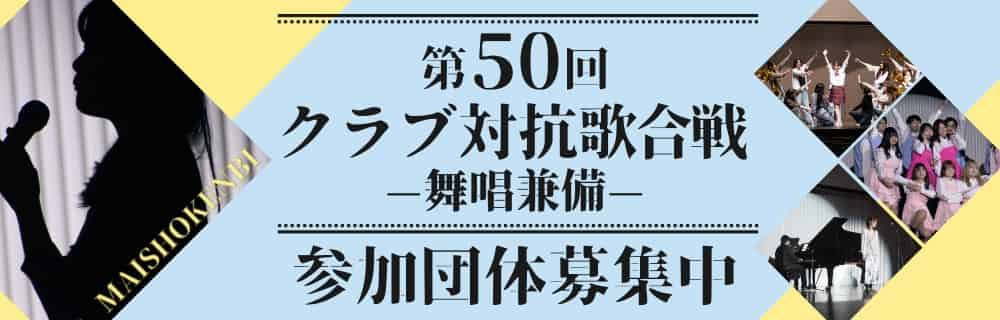あなたも装飾企画に参加しよう!
このページでは装飾という企画形態についての説明やその魅力、支援制度についてまとめています。
装飾と聞くとハードルが高く感じる方もいるかもしれませんが、比較的低いコストで屋内の装飾企画へ参加することも可能です。また、装飾援助制度や備品貸し出し制度といった企画支援制度も用意しております。初めての方でも、担当が全力でサポートしてまいります!他企画形態と両立もしやすいのでぜひご覧ください!
装飾企画とは
その名の通り一橋祭を彩る装飾物を展示する企画形態です。立て看板にデザインを施す「立て看板形式の装飾物」とオブジェなどの立体装飾を含む「屋外設置の自由形式の装飾物」、講義棟の階段の踊り場や廊下などの屋内のスペースに装飾物を設置する「屋内設置の装飾物」の3通りの方法でご参加いただけます。
初めて装飾企画に参加される方でもお気軽に参加できるように担当(樽木:iks56th.decoration@gmail.com)が全力でサポートいたします。一橋祭当日は企画者が常駐する必要がないので、他企画形態との同時参加もしやすくなっております。個人で参加していただくことも可能です。一橋祭であなたの世界観を自由に表現してみませんか?
昨年度の様子
「あのひ 夢にみたもの」
一橋大学津田塾大学合唱団ユマニテ
初めての方でも大きな装飾物を制作できます。

「アニバーサリー看板」 GT会
木材でオブジェを制作することもできます。

屋内を彩ろう!
講義棟の階段の踊り場や廊下など屋内の人の目に触れやすい空間に作品を展示することができます。下の写真のように比較的広いスペースを使うことができるので、大きなサイズの絵などの装飾物を展示することができます。参加に必要なコストも低く抑えられるため、一橋祭に作品を展示してみたいけれど立て看板形式の装飾物はハードルが高い、という方にもおすすめです!
疑問があれば……
上の写真で例示した装飾物、企画場所以外でも屋内で装飾企画に参加することができます。装飾物や企画場所、設置方法についての疑問点や参加にあたって不安な点がございましたらお気軽に担当(樽木)までご相談ください。
装飾企画の支援制度
装飾援助制度
作品を制作するうえで必要な角材、ベニヤ、ペンキなどの品目を弊会がご用意する制度です。援助する品目は提出された申請をもとに決定します。金額には限りがあるため、一部またはすべての品目について援助を行うことができない場合があります。装飾援助の対象外となった品目や装飾援助の申請を行わなかった品目であっても、引き渡しの際に代金を徴収する形で弊会が購入するため、必要な品目を用意する手間を省くことができます。
備品貸し出し制度
作品の設置にかかわる備品や作成に必要な工具などを貸し出せる場合がありますのでお気軽にご相談ください。
立て看板の作り方の例
2つの参加形態のうち立て看板形式についてご紹介します。一見手間がかかりそうな立て看板も、以下のステップで誰でも簡単に作成することができます。
1
デザインを作る、実寸大にする
Inkscapeという無料ソフトを用いてパソコンでデザインを作ることを推奨します。作るデザインは印刷の関係上実寸大にします。
1枚看は92cm×183cm、3枚看は183cm×276cmです。「ファイル>ドキュメントのプロパティ」から変更が可能です。その他の基本操作については直接お教えすることも可能ですので担当(樽木)までご相談ください。
※Inkscape以外のツールでもデザインの作成は可能です。
2
色抜きする
ベニヤに転写する際に必要なのはデザインの外線のみなので、それ以外の色を白にするとインクを節約できます。また、黒のインクの消費量を減らすために外線も透過度50%程のグレーにします。「ファイル>名前を付けて保存」からPDFファイルで保存して印刷に移ります。
3
デザインを印刷する
PDFから印刷を行います。PDFをAdobe Acrobatという無料ソフトで開き、印刷設定を以下の通りにして実行します。
| 変更箇所 | 変更点 |
|---|---|
| プリンター | お手持ちのプリンターの名前に変更します。 |
| プロパティ | A3・モノクロ・片面印刷にします。 |
| ページサイズ処理 | 「ポスター」を選択し、「ラベル」と「タイルマーク」にチェックを入れます。 |
この際デザインが書かれていない白紙も印刷されますが、抜かしてしまうと並べる手間が増えるため、白紙も含めて印刷してください。また、変更できない場合は「詳細設定」で設定できる場合がありますのでそちらをご確認ください。
4
下塗りをする
下塗りとは、すでにデザインが描かれている看板に転写しやすくするために、全て同じ色のペンキで塗るという工程です。効率的に塗るために、一度に塗れる面積の大きいブラシやローラーを用います。下塗りをした看板はペンキを乾かすために1日程度放置する必要があります。ペンキが乾くまでは転写の作業に移ることができないので作業予定には余裕を持ってください。
5
カーボン紙を用いて転写する
印刷したデザインの描かれた紙を養生テープで貼り合わせます。貼り合わせたら、その紙と看板をテープで貼って固定します。続いて、看板とデザインの描かれた紙の間にカーボン紙を入れて、ボールペンで上からなぞります。カーボン紙とは一般的に転写に用いる用紙です。カーボン紙には色が移る面と移らない面があるので、色が移る面が下になるようにしてください。常になぞっている箇所の下にカーボン紙がくるように、カーボン紙を動かしながら転写します。
6
ペンキで塗る
転写された線に沿ってペンキで塗ります。看板の中央から塗り始めると作業が楽に進められます。その際、ベニヤの上に乗ることもあるかと思いますが、体重をかけすぎるとベニヤや角材が割れてしまいます。裏に角材があるところに手をつきながら塗ってください。
一橋祭までの大まかな流れ
-
6/25(水)
- 装飾企画についてや一橋祭に参加するうえでの注意事項などを説明いたします。
-
7/1(火)
7/3(木)
7/10(木)
7/11(金) -
7/11(金)
- 締切までにこちらのページの各種フォームにて装飾企画の参加手続きを行ってください。
-
7月中旬
- 制作方法、作業場所、備品、設置場所の希望などについて全団体と個別にご相談の機会を設けます。また、装飾援助を希望する品目や制作に使用する品目の相談、申請も行っていただきます。皆さまのアイデアを形にするために全力でサポートいたします!
-
8/1(金)
- 7月中を目途にどのような装飾物を制作するのかを決定します。夏休みでの作業予定なども決めていただきます。
-
8月中旬
以降- 制作物に合わせて角材、ベニヤ板などの品目の引き渡しを行います。また、このタイミングで参加金・保証金を徴収いたします。
-
夏休み
期間中- 実際に作品を制作していきます。頭の中にあった世界観が実際に目の前で形になっていく過程はとても楽しいです。
-
11/21(金)
準備日- 作品を委員の立ち合いのもとに設置します。自分の手で一橋祭を彩り、来場者が実際に楽しんでいるのを見ると達成感があふれ出すこと間違いなしです!